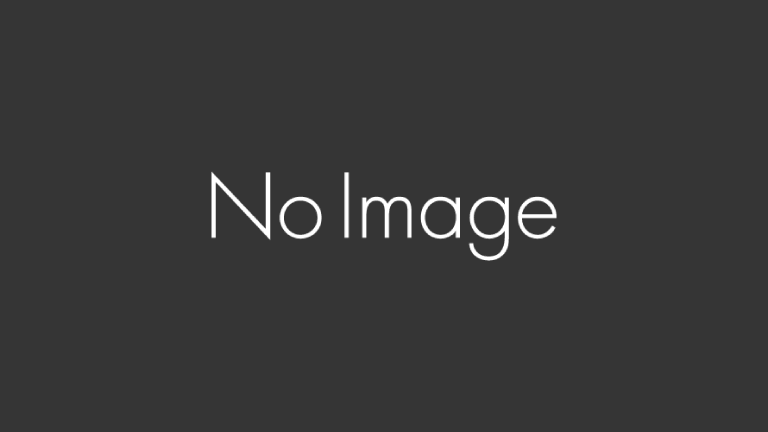“紙媒体を通して、関わる方々を応援する”
これが株式会社九秀製本ドットコムさんの経営理念。
第一回目のインタビューでは宮地啓一社長と専務の宮地恭平さんにお話をうかがいました。
特に、“紙は生き物である”というお話が印象的。
製本というお仕事は“機械”を使っていますが、単純なライン作業ではなく、生き物である紙と日々向き合うモノづくりなんです。
第二回目となる今回は、実際にモノづくりの現場で働く村上千春さん、宮地祐樹さんにお話をうかがいました。
紙媒体に関わるお仕事に就きたい!本に携わりたい!という思いを持っている方は必見!
ぜひ最後までご覧ください。
九秀製本ドットコムが語る”紙はファンタジー“
今回インタビューしたのは株式会社九秀製本ドットコム(以下:九秀製本ドットコムさん)入社19年目の村上千春さん、入社15年目の宮地祐樹さん。
毎日“紙”と向き合うお二人に、紙という生き物に対する印象をおうかがいしてみました。

日々“紙”に触れていますが感じるのは、やはり“紙”は生きているということ。
いつも違う表情を見せるのが紙なんです。
例えば紙を裁断する作業において、昨日と同じ切り幅で紙をセットすることはできません。
紙は湿気で伸び縮みしますし、静電気でくっついてしまったりするんです。
だからこそ紙は生きていると感じますし、この仕事の一つの魅力かなと思います
第一回目のインタビューで宮地社長は“製本業はファジーな世界。つまりとても曖昧なんです”とお話していました。
規格は定められているものの規格通りに紙が収まってくれることはない。
だからこそ現場で働く方には技術が求められるし、機械だけに任せることはできない仕事だと言います。

宮地さんは紙に対してどんな印象を持っているのでしょうか。

村上さんと同じで、昨日はこんな感じの設置の仕方で良かったのに次の日になると“昨日と違うじゃん!”とびっくりすることがあります。
あとは、紙というのは人の生活の中で何かを思い出させてくれることがあると思います。
例えば電子書籍がありますよね。電子書籍はかさばらずに本を持ち運ぶことができますし、気になる本をほぼノータイムで購入することもできます。つまり利便性がとても高いと思うんです。
ただ、自分が“本を読もう”と思わなければ目に入らない媒体でもあります。
これに対して紙媒体はカタチあるモノとして身の回りに存在するので、目に入るとついつい本やマンガを手に取るということもあると思うんです。そうやって存在を思い出させてくれるのが紙媒体です。
それ以外に、紙媒体は本や漫画の内容以外のことも思い出させてくれます。小さい時に好きだったマンガを手にとってみると、ちょっとした汚れがついていたり、どこか懐かしい香りがしたり。
マンガの内容以外にも、自分の大切な記憶を思い出させてくれます。
製本業は社長はファジーな世界だと言っていましたが、それに加えて紙媒体にはファンタジーチックな側面もあると思います
宮地さんの“紙媒体は何かを思い出させてくれる”というお話。皆さんもご経験があるかもしれません。
数年前に読んでいた本を手に取ると、本の内容を思い出すだけではなく当時の思い出がどんどん蘇ります。
こうやって人の暮らしを彩ってくれる紙媒体。
そのうち、最終的に皆さんの手元へ届く形にするために行うのが製本という作業。
九州でもトップレベルの技術を持って製本業を営むのが九秀製本ドットコムさんです。

紙媒体でみなさんの生活を支える
続いてお二人におうかがいしたのは“製本”というお仕事のやりがい。
ここまでのお二人のお話から“製本は単なる作業ではない”ということは感じられますが、お仕事において感じるやりがいとはどのようなものでしょうか。

街中で誰かが本を読んだり雑誌に目を通しているのを見た時に嬉しくなります。
どんな仕事でも結果が求められますし、だからこそ皆さん一生懸命仕事をしているのだと思いますが、九秀製本ドットコムの仕事の結果は目に見えるものです。
紙の機嫌が良くても悪くても、どうにかして質を落とさずに製本を仕上げる。
そうやって自分が頑張った結果が皆さんの手元へ届く、そしてカタチとして結果を見ることができる。これがこの仕事の一番のやりがいだと思います。
本やマンガの内容を作成しているのは自分ではありませんが、自分が製本した本を手にとって楽しんでいる方を見かけると、また明日からもっと仕事頑張ろう!と思います。
九秀製本ドットコムの経営理念はこういうことなのかなと思うんです。
直接的でも間接的でも、紙というカタチを通して人の暮らしを彩る。紙だからできることを信じて仕事に打ち込む。
そうやって理念に向かって仕事をしていきたいなと感じています
“紙”を扱うことが簡単ではないからこそ感じるお仕事のやりがいなのかなと考えました。
もし紙が生き物のように表情を変えないモノだとしたら、製本の仕事は機械だけでまかなうことができるかもしれません。
しかしそうではないからこそ、苦労や楽しさややりがいがある。
“製本業”の魅力に今回も惹き込まれていきます。

続いて宮地さんにもお仕事のやりがいをうかがってみました。

自分は機械を扱うことにとても楽しさややりがいを感じます。
もともと機械が好きだったというわけではないのですが、この仕事を始めてから楽しさややりがいに気づきました。
製本の仕事というのは質を落とさないことが重要ですが、スピードも求められるものなんです。
1日に10万冊製本することも当たり前のようにあるんです。なので、その日の紙の調子や、紙一枚一枚の特徴を理解しながら、質もスピードも落とさないように機械を動かします。
そこに自分の技術や実力が関係してくるからこそ、機械を扱うことに楽しさを感じています
10万冊という、想像をはるかに超える製本量に驚き!
ですが、以前九秀製本ドットコムさんの工場へ見学にお伺いさせていただいた際に、とんでもない量の“紙”が積み上げられていることを思い出しました。
他に劣らない技術を持ちつつ、スピードにもこだわる。
モノづくりの職人のプライドを感じる宮地さんのお話でした。

九秀製本ドットコムさんが目指すは“和”
ここまではモノづくりの現場で働く村上さんと宮地さんに、“紙の魅力”紙に携わる“お仕事のやりがい”についてお話いただきました。
続いておうかがいしたのは九秀製本ドットコムさんの働く環境について。
現場で働くお二人が見る、九秀製本ドットコムさんの実態に迫ります。

組織として“和”を目指すことを意識して日々仕事をしています。
ここまでの話にもあるように、製本の仕事というのはモノづくりです。
なので、現場で働く人は“職人さん”なんです。
“職人さん”というと気難しいとか寡黙とかそんな印象を持たれるかもいるかと思いますが、以前は実際にそんな感じの方も多かったんですね。
ただ、それでは業務の結果は属人的なものになってしまいますし、部門に一人しか職人さんがいない場合は、その職人さんがお休みするだけで生産性がガクッと落ちてしまうんです。
だからこそ“和”をテーマに掲げて社内の環境作りを始めました
確かに職人さんというと宮地さんがお話しされたような印象を持ちます。
ただそれでは良くないということで掲げた“和”というテーマ。テーマに対して具体的にどのようなことを行ったのでしょうか。

組織の雰囲気という面と具体的な業務の面、の2つを改善しました。
組織の雰囲気の面だととにかくコミュニケーションをとるようになりました。
社内のコミュニケーションが円滑になるように、中間管理職のような立場にいる自分と宮地から、頻繁にコミュニケーションをとったんです。
今の立場になる前は自分も職人の一人として仕事をしていたので、今の職人さんに共感できる悩みもありましたし、自分も困っていたよなということを思い出したりしました。
そうやって地道ですがみんなの声を聞いて、より働きやすい環境つくりを心がけていったんです
やはり社内のコミュニケーションはとても重要だとお二人は話してくれました。
気軽に話しやすい環境を作っていたとしても、社員さんは仕事におけるお困りごとを全て話してくれるわけではない。
だからこそ社長と社員の間に位置する自分たちが、社員さんとコミュニケーションをしっかりととって、小さな変化にも敏感になることが重要だと話してくれました。

業務の面においては“和”を目指してどのようなことを行ったのでしょうか。

製本で扱う機械は意外とたくさんあるんです。
紙の綴じ方によって機械も異なりますし、持ち込まれる紙の種類によっても機械は異なります。
そして紙は生き物ですから、一つの機械の扱いに慣れるまでに時間がかかるものなんです。
なのでこれまでは一人が一つの機械を習熟していくというようなスタイルで業務を進めていましたが、それでは困ることが多かったんです。
そこで、一人がいくつかの機械を動かせるように部門間で連携して勉強をしました。
そうすることで一人の職人さんに依存してしまう組織体質から抜け出すことができましたし、一人への業務負担も減らすことができました
組織として“和”を目指すうえで、雰囲気の面、業務の面、両方から工夫を施している九秀製本ドットコムさん。
そして、この“和”という文字にも思いが込められていました。

組織の“わ”というと、“輪”という漢字が用いられることもあると思うんです。
ただ九秀製本ドットコムではあえて“和”という漢字にしました。
九秀製本ドットコムは機械的に、もしくは規律的に社内のあらゆる導線を整えてスムーズな動きを目指す“輪”ではなく、互いのコミュニケーションや情報共有を行うことによって悩みや困りごとを無くし、人間味のある一つの集団として存在する“和”を目指しています。
紙が日々違う表情を見せるように、会社というものも人が集まった組織なので“いつも同じ”では不自然ですし、“いつも同じ”では楽しさややりがいを失っていくと思います。
だからこそ九秀製本ドットコムは“和”を目指して、技術の高い職人が集まる製本会社としてこれからも紙媒体を通して皆さんを応援したいんです

現場で働く人まで機械のようになってしまっては働くことの楽しさも組織だからこそのやりがいもなくなってしまいます。
だからこそ社員みんなで“和”を目指す。そして自分たちの技術もどんどん高めて他にはできないモノづくりをする。
そんなことを考えながら日々仕事をしています
九秀製本ドットコムさんのお話をうかがって
今回は九秀製本ドットコムさんに第二回目の取材をしました。
生き物である紙と毎日触れ合う現場の職人さんだからこそ感じる、“紙の魅力”や“製本業のやりがい”についてたくさん教えていただくことができました。
第一回目の取材では宮地社長から“紙はファジーである”という素敵な言葉をいただきましたが、今回は“紙はファンタジーでもある”という素敵な言葉をいただきました。
「紙媒体市場はどんどんと小さくなっている」 デジタルが発達し、スマートフォンやパソコンから情報に触れることが当たり前になっている世界。 そこで過ごす私たちが、紙媒体市場に対してこんなイメージを抱くことはおかしくありません[…]
ナビラズではあと一回、九秀製本ドットコムさんにインタビューをします。
次回も紙に対するどんなお話が聞けるか楽しみですね!
九秀製本ドットコムさんのことが気になった方はぜひHPもご覧ください!
九秀製本ドットコムは低コスト・短納期を重視し、常に時代を先取りした設備を揃えています。製本のことなら全国に3台、九州では…